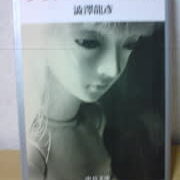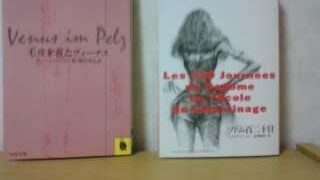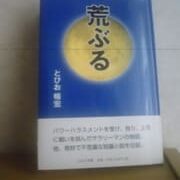文学
文学 能楽
最近、能楽の全集を手に入れ、これをぱらぱらとめくっています。 もとより、私は能楽に関しては数回の鑑賞経験があるだけの、素人です。 日本の古典文学は、美と仏教とが融合したものと思われます。 古くは、美を代表する「源氏物語」や「新古今和歌集」などと、仏教を題材とする「今昔物語集」などに二分されていたように思いますが、能楽の完成に至って、これらは融合されました。 幽玄の美、と称せられる能楽には、たいてい、僧侶ともののけが同時に登場します。言うまでもなく、もののけは、美や、この世ならぬものへの予感、つまり芸術そのものを表し、僧侶は仏教哲学を代表します。これらが互いに主張したり、戦ったり、最後には大団円へと向かうさまは、圧巻です。 能で演奏される音楽も、見事にそれらの融合を表しているように感じられます。 最大の難点は、能面をかぶったりしているため、セリフが著しく聞き取りにくく、眠気を誘うことでしょう。