 美術
美術 激動の時代の芸術
今日は千葉市美術館に出かけました。 ある方から招待券を頂いたので、たいして興味のない展覧会でしたが、もったいないので。 1968年激動の時代の芸術、というのを観てきました。 千葉市美術館は、市立にしては予算があるのか、鏑木清方展など、洒落た展示をやるので、好事家の間では有名ですが、今回のはいただけません。 美術というより、特殊な時代を懐かしむだけの展示でした。 がっかり。
 美術
美術  美術
美術  美術
美術 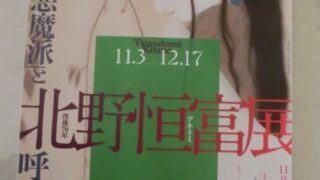 美術
美術  美術
美術