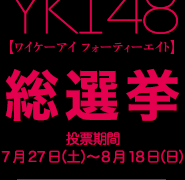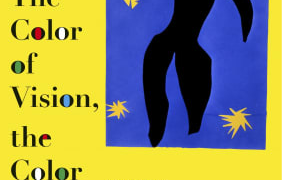美術
美術 遷御の儀
今夜、いよいよ伊勢神宮の内宮で式年遷宮のクライマックスとも言うべき遷御の儀が営まれますね。 ご神体が新正殿に移る儀式です。 150人もの神職が式年遷宮のためだけの衣装に身を包み、厳かに行われます。 それにしても式年遷宮とは世界に例を見ない不思議な儀式です。 20年ごとに社殿を全て新築するのですから。 一説には、1300年ほど前から行われているとかで、古い技術の継承や、清浄を重んじる神道の精神から、天照大神を祀る伊勢神宮の社殿は常に新しいほうがよい、と言ったことが理由と考えられますが、正確にいつ、どういう理由で始まったかは謎のままです。伊勢神宮のこころ、式年遷宮の意味小堀 邦夫淡交社 近年のパワー・スポットブームで、伊勢神宮にお参りする人はずいぶん増えているようです。 近代建築に大きな影響を及ぼしたブルーノ・タウトが、伊勢神宮を訪れて、「稲妻に打たれたような衝撃をうけた」と語ったのは、有名な話です。 また、ノイトラは、桂離宮をはじめとする、わが国の伝統建築に接し、「私の空間の処理と自然に対する感性と、完全に一致した。私は生涯求めてきたものに出会った。私はもはや孤独ではなかった」と、絶賛...