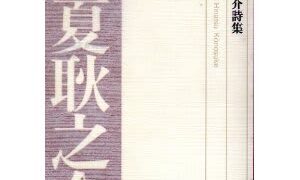文学
文学 弁天小僧
近頃私は、仕事を終えて帰るなり、一杯やりながらユー・チューブで落語を楽しむのを常としています。 お気に入りは、今は亡き古今亭志ん朝師匠。 爽やかな江戸弁と、すっとこどっこいな感じ、それに色気がたまりません。 今日は珍しく、ユー・チューブで歌舞伎を鑑賞しました。 出し物は、「弁天娘女男白浪 」。 尾上菊五郎、中村吉右衛門、松本幸四郎などが出演する、豪華な演目です。 私はなにしろ当代の菊五郎が贔屓で、その姿、声、しゃべりを観ていると、うっとりしてしまいます。 さすがに今となっては老いてしまいましたが。 菊五郎は、声よし、姿よし、顔よし、で、難をつけるところが見当たりません。 強いて言えばたっぱが低いことですが、それとて江戸っ子らしくてよろしく思えます。 ウドの大木みたいな江戸っ子では、観ているほうが白けるというものです。 何度か、歌舞伎座や国立劇場で菊五郎の芝居を観ましたが、私はもういっちゃいそうです。 で、今日観た芝居は、さる大名のお嬢様に化けた菊五郎演じる弁天小僧が、仲間とともに呉服屋に騙りに入り、もう一歩で百両せしめようと言うところ、悪事が露見してしまうというシンプルなお話。 弁天...