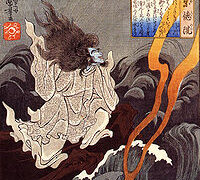文学
文学 雪見
もう私が働く職場の庭では、梅がふくらんでいます。 それなのに今日は午後から雪になりました。 雪が降ると寒いですねぇ。 幸い積もることはなさそうです。 梅の花 それとも見えず 久方の 天霧る雪の なべて降れれば よみひとしらず 「古今和歌集」に見られる歌です。 春の雪で、梅の花が雪にまぎれてそれと分からない、という情景を詠んだ、寒々しいような、春が待ち遠しいような感じがよく出ていますねぇ。 手だれによる和歌と思われますが、よみひとしらずなんですねぇ。 では敬愛する蕪村先生は雪見をなんと詠んでいるでしょう? いざ雪見 容(かたちづくり)す 蓑と笠 与謝蕪村 蕪村は放浪の後、京都に居を構え、二度と旅に出ることはありませんでした。 芭蕉に比べ、軟弱な都会人だったのですねぇ。 さあ、雪見だ、といって重装備をする姿が、都会的と言えば都会的、大げさといえば大げさ。 京都ごときでそんなに降らないでしょうにねぇ。 どちらにしても、そこはかとないユーモアが漂います。 風狂の人の句ではありえませんねぇ...