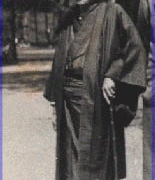文学
文学 迎春
新年あけましておめでとうございます。 このブログを愛読くださる皆様全てのご多幸をお祈り申し上げます。 私は今日親戚の家で昼から新年会。 明日は夜実家で新年会です。 今年は、 目出度さも ちう位也 おらが春 という小林一茶の句のような気分が日本国中を覆っています。 小林一茶は、ことしの春もあなた任せになんむかへける、と俳文集「おらが春」につづっています。 阿弥陀仏による他力本願を深く信仰していた彼は、正月を迎えるのもあなた任せ、つまり阿弥陀仏の力によるものだと言っているわけで、大海を小船で漂流しているような人の生において、人間の自力では何事もどうにもならないと、信仰告白をしているものと思われます。 私は浄土教の教えである他力本願を信仰するものではありませんが、小林一茶の信仰告白には心打たれます。 今年一年を無事に過ごせるかどうかは、それこそお釈迦様にもわかるめぇと思いますが、今日一日だけは働くのだ、明日は知らんのだ、という一日出勤を積み重ね、お給料をもらいたいと思っています。 幸い今の部署は性に合っているようで、苦痛ではありません。 それどころか、たまには面白いと思うことさえあります。 ...