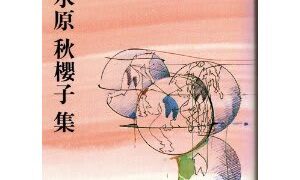文学
文学 戦争の法
現在活躍中の小説家で、最も上質という言葉が似合うのは、佐藤亜紀だと思います。 最近は早稲田大学や明治大学の客員教授として創作の作法を教えているとか。 たいそうなご活躍です。 主にヨーロッパを舞台にした作品が多いですが、「戦争の法」は日本を舞台にしていて、しかもどこかブラック・ユーモアみたいなものが効いている異色の作品です。 平野啓一郎が「日蝕」をひっさげて颯爽とデヴューした時、佐藤亜紀は自身の作品「鏡の影」のパクリだと、小説家にとってはこれ以上ない侮辱を浴びせたことを懐かしく思い出します。 平野啓一郎は佐藤亜紀なる小説家の存在も知らないし、その作品を読んだこともないし、今後も読むことはない、と完全否定しました。 佐藤亜紀はこれに対し、盗作をしたかどうかはともかく、彼が嘘つきだということははっきりした、と言って応戦しました。 「鏡の影」も「日蝕」も新潮社から出版されていたところ、新潮社は「日蝕」の出版に合わせるように「鏡の影」を絶版にしてしまいました。 二人を比べて、平野啓一郎の将来性に賭けたということでしょうか。 しかし、現在の活躍を見る限り、新潮社の判断が正しかったとは言い難い状況で...