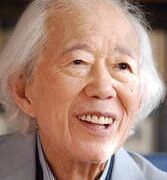文学
文学 立冬
今日は立冬ですね。 心なしか冬の香が漂ってきたような。 私はスリムだった頃、夏以外はみな寒く感じました。 20キロ増えた今は、冬以外の季節は暑く感じます。 どちらが楽かといえば、今の方が楽ですねぇ。 寒いのは辛いですから。 体重が増えた効用です。 大切な もの皆抱へ 冬に入る 黛まどか 私はこの俳人の、反則すれすれの句が気に入っています。 現代俳句の新しい地平でしょう。 現代語で短歌をひねる俵万智とは似て非なるものです。 俵万智の短歌はおそらく時代とともに風化していくものと予想しますが、黛まどかの俳句は平成の俳句刷新として長く文学史に語り継がれるでしょう。 団栗の 拾はれたくて 転がれり 黛まどか こちらは厳密に言えば秋の句ですが、立冬の時期が気候で言うと秋真っ盛りですから、堅いことは抜きにしましょう。 むしろ今の時期、秋の季語で句を詠むのが季節の実感に合っていると言えるでしょう。 これから日ごとに寒くなっていくのが、なんだか楽しみのような気がします。 首都圏くらいだったら、夏より冬のほうがすごしやすいですからねぇ。 そういえば知り合いの某ニュー・ヨーカーが、「東京に冬はない、長...