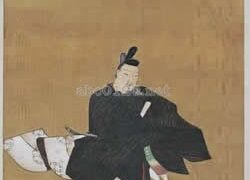文学
文学 「エーゲ海に捧ぐ」と「僕って何」
古い話で恐縮ですが、文芸春秋が売上100万部を超えたのは、「エーゲ海に捧ぐ」と「僕って何」が芥川賞を同時受賞したときと、「昭和天皇独白録」を掲載したとき、村上龍の『限りなく透明に近いブルー』が掲載されたとき、金原ひとみの『蛇にピアス』と綿矢りさの『蹴りたい背中』が掲載された時の、わずか4回だそうです。 「エーゲ海に捧ぐ」と「僕って何」の組み合わせ、絶妙であったとみえます。 前者はきんきらきんに光り輝く、神話的な性愛の世界を描く耽美的なもの。 後者は学生運動に身を投じてなれないヘルメットに角材で武装して、街頭活動をやってみるものの、すぐに逃げ出して、僕って何者なんだ、と自問自答するという地味でありがちな湿っぽい青春文学。 両者は正反対のようでいて、意外にも共通点を持っているように思います。 「僕って何」の作者、三田誠広は、高校時代、学生小説コンクールでグランプリをとっています。 それがまた、くらぁい小説なのですよ。 「Mの世界」というのですが、おそらく著者自らのイニシァルからとったと思われるMなるやつがぐじぐじぐじぐじ思い悩んで、最後は自殺を図るという、わが国近代文学のつまらないエキスば...