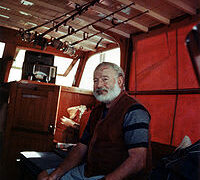文学
文学 二百十日
早いもので、明日は二百十日。 台風が多いとされる季節です。 昔の人が言うことは当たり、今、大型の台風が日本列島に向けて接近中。 土曜日には、最接近するとか。 今は気密性の高いマンションに住んでいますから、台風が来たところでなんともありませんが、子どもの頃住んでいた家は違いました。 台風がくると、まず木製の雨戸を閉めます。 雨戸を閉めれば大丈夫かというとそうでもなく、雨戸、ガラス戸が風で大きな音を立てます。 ところどころ雨漏りがするので、その下にバケツを置きます。 そんなことの一つ一つが、幼い私を、お祭りのようなわくわくする気持ちにさせました。 その実家も、私が中学1年生の時に立て替えて、台風にまつわる昭和らしい思い出は、途切れてしまいます。昭和57年、昭和が終わる7年前の出来事です。 夏目漱石に「二百十日」という小説がありますね。 阿蘇登山の間抜けな顛末を語りながら、主人公の金持ち批判、庶民に頭の革命を起こす、といった血気盛んな感じと、相棒の、のんびり観光を楽しもうという態度が対照的で、落語の「長短」を聞くような滑稽味があります。 夏目漱石が神経症的な作品を連発する前の、乾いた文体が魅...