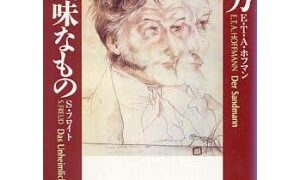文学
文学 梅雨明け
今年は早くも梅雨があけて、暴力的なまでに強烈な陽射しが降り注いでいます。 昨日ははるばる日本橋の三井記念美術館まで足を運びましたが、今日は冷房を効かせたマンションから出ることができません。 まことに狂気じみた暑熱で、我が家に節電という言葉は存在しえません。 この必ず訪れる過酷な暑さを、古人はどう過ごしていたのでしょうね。 入道の 裸うとまし 竹婦人 内藤鳴雪 入道はもともと坊主になって修行する人のことですが、この句ではむさくるしい大男と思えばよいかと思います。 竹婦人とは竹で編んだ抱き枕で、涼をとるための物です。 大男の裸が鬱陶しい、と竹婦人が思うほどの、うだるような熱帯夜を、洒落た句で表現していますね。 なるほど古人は、こんな風に熱帯夜を過ごしたのでしょうね。 ゆるやかに 着てひととあふ 蛍の夜 桂信子 こちらはぐっと意味深な句ですね。 浴衣をゆるやかに着て蛍の夜にひとと会うというのです。 夏の夜のデートでしょうか。 暑いのがかえって肉感的な興趣を高めています。 こんな過ごし方なら、蒸し暑い夜も、心騒ぐものとなりましょう。 しかしすだれをかけても風鈴を鳴らしても打ち水をし...