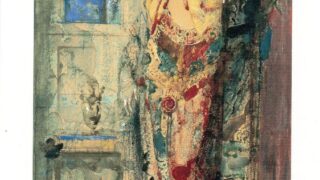文学
文学 台風一過
台風らしからぬ台風が行ってしまい、しかし台風一過らしい暑さがやってきました。 私が執務する部屋は西日があたり、エアコンをかけていても午後はむうっとする暑さです。 お手討ちの 夫婦(めをと)なりしを 更衣(ころもがへ) 与謝蕪村の句です。 更衣は夏の季語。 不義密通の罪で処刑されるはずのところ、罪一等を減じられて他国へ落ち延び、ようやっと二人で更衣の季節を迎えられた、といったほどの意でしょうか。 色っぽくも切ない内容で、夏の句らしからぬ情趣を感じます。 涼しさや 鐘をはなるる かねの声 こちらも与謝蕪村の句。 鐘がなるたびにその音は離れていく、ということで、爽やかな印象とともに、どこか寂しさも感じます。 郷愁の詩人と呼ばれた面目躍如といったところでしょうか。郷愁の詩人 与謝蕪村 (岩波文庫)萩原 朔太郎岩波書店 私は俳人のなかではこの人の句を最も愛好しています。蕪村俳句集 (岩波文庫)尾形 仂岩波書店 ただ、わが国の文人の例にもれず、この人も夏を詠んだ句は少ないようです。 夏と言う季節は、わが国の詩歌の美意識に合わないのかもしれませんね。 暑すぎて閉口しますから。 日傘の影 うすく恋して...