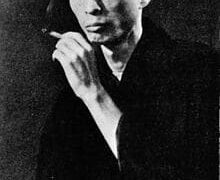 文学
文学 川端康成先生、安らかに
1972年の今日、ノーベル文学賞作家の川端康成先生が逝去されました。 ガス自殺と伝えられます。 戦後、「私はもう日本の美しか詠わない」と宣言され、官能的な作品や美的な作品を生み出し、それが評価されてのノーベル文学賞受賞だったと思われます。 授賞式には燕尾服ではなく、紋付き袴姿で臨み、あくまで日本の美を追求する姿勢を鮮明にされましたね。 その姿、1968年、政治の季節の真っ最中だった日本の人々に強い印象を残したであろうことは、想像に難くありません。 遺書はなく、老醜をさらしたくなかったのでは、と憶測を呼びました。 「美しい日本の私」と題した受賞記念講演では、道元禅師の、春は花 夏ほととぎす 秋は月 冬雪さえて すずしかりけり という和歌を朗吟し、ためにこの歌が人口に膾炙するようになったと言っても過言ではありません。道元の和歌 - 春は花 夏ほととぎす (中公新書 (1807))松本 章男中央公論新社 三島由紀夫を見出したことでも知られ、彼は川端先生を師と慕いました。 三島由紀夫が男色家であったことは公然の秘密ですが、川端先生はたいそうな女好きで知られていました。 純文学だけではなく、中原...
