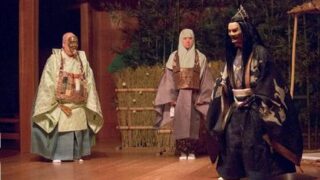文学
文学 寒露
今日は二十四節季の17番目、寒露ですね。 「暦便覧」では、陰寒の気に合つて露結び凝らんとすれば也と説明しいています。 また、他の辞書では、雁などの冬の渡り鳥が渡ってきて、蟋蟀が鳴きやむ頃、とも。 ひらたく言えば、秋が深まり、そろそろ冬が近付く頃ということでしょうが、毎度のことながら、旧暦の暦を新暦に合わせることなく、日付けをそのままにしているのは奇妙な感じがして仕方ありません。 新暦と二十四節季が合うようにしないと、二十四節季なんて、観念上の遊びに堕してしまいます。 新室に 歌よみをれば 棟近く 雁がね啼きて 茶は冷えにけり 正岡子規の和歌です。 ちょうど寒露の頃を詠んだものと思われます。 茶は冷えにけり、というのが、いかにも冬の到来を実感させますねぇ。子規歌集 (岩波文庫)土屋 文明岩波書店 しかし、今日の首都圏はかなり気温が上がりそうです。 多分25度は超えるでしょう。 実感としては、まだ初秋の気分です。 唯一、日が短くなったことが、秋を感じさせます。 秋から冬にかけて、なんとなく気分が沈む季節。 しかも年度末に向かって仕事量が増えて行きます。 ここは抗うつ薬を頼りに、出勤を続け...