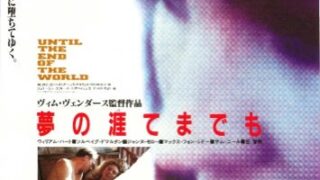思想・学問
思想・学問 黄泉に行く
汝の敵を愛せ、とキリストは説いたと伝えられます。 これは普通に考えれば到底受け入れがたいことです。 受け入れがたいことを受け入れるから立派な行為だとされるのでしょうね。 ただし、ただ単純に敵を愛するというよりも、敵を愛するという行為が、神様を愛するという行いにつながり、もって、人は神を愛し、愛される、という理屈のようです。 それによって、天国の門が開かれる、という利益が得られるというわけで、神の愛は無償かもしれませんが、人の愛はどこまでいっても対価を求めるもののようです。死ねばみな 黄泉に行くとは 知らずして ほとけの国を ねがふおろかさ 本居宣長の和歌です。 この人、日本神話に書かれていることを頭から正しいと信じ、仏教を批判しました。 神話では、黄泉の国は穢れた場所だとされていますから、誰だってそんなところに行くよりも、極楽往生を遂げたいと思うのが人情でしょうに。 この人、仏教や儒教などに侵されたわが国の思想体系を深く憂い、大和心をこそ良しとして、その本質に迫ろうと、「古事記伝」などの大作や、「源氏物語玉の小櫛―物のあわれ論」を著しました。古事記伝 1 (岩波文庫 黄 219-6)倉...